小泉八雲特集 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ラフカディオ・ハーン (小泉八雲)
一ギリシャ人研究者としての見解 クレリ・パパパヴル博士インタビュー (概要)
1. ラフカディオ・ハーンの履歴、ハーンの特徴
(1) ハーンの生涯 自分(以下、パパパヴル博士)がハーンを「三大陸のオデュッセウス」と名付けた理由は、ハーンの活動範囲と人生が、ヨーロッパ、アメリカ、アジア(つまり日本)にほぼ等しく跨っているためである。ハーンはオデュッセウスのように波乱に満ちた一生を送ったが、彼に対し「オデュッセイア」の言葉を最初に使ったのは非ギリシャ人の研究者だった。自分が著した本の中には『もう一人のラフカディオ・ハーン』があるが、この題名はハーンの多様で豊かな人格、事物に対する広範な関心、全く異なる表現形式を自在に駆使する筆致を表すために付けた。 (2) ハーンの人生の三つの時代 (ア) ヨーロッパ時代 第一の時代であるヨーロッパ時代が最も波瀾万丈だった。ハーンが生まれた1850年代はギリシャのエプタニサ諸島は英国領で、母親のローザ・カシマティはキシラ島に住むギリシャ人、父親のチャールズ・ブッシュ・ハーンはアイルランド人軍医であった。両親はレフカダ島で結婚するが 1、父親は再び転任し、幼いハーンは人生最初の2~3年間を母親と二人きりで過ごした。長男 2の早すぎる死に傷ついたローザの愛情はハーンに集中して注がれた。後にハーンは、幼い彼のベッドにかがんで指で十字を切らせる時の母親の大きな黒い瞳や、彼を諭すために呼ぶ母親の声等について三人目の弟に書簡で色々と打ち明けている。ギリシャでの牧歌的な時代は、アイルランドに移住した時に終った 3。アイルランドでは、プラスともマイナスとも、その両方とも取れる様々な方向にハーンは進んだ。例えば、アイルランドのどんより曇った風景や、ケルト人の神秘的な城から受けた影響によりハーンの想像力は豊かになり、怪談や怪奇物語への傾倒を育んだ。ハーン家の豊富な蔵書により古代ギリシャ文化に触れた。両親が離婚し、母親と離別した4。父親は早々に再婚5したが他界してしまい、ハーンが父親と会ったのは7歳の時が最後だった。ローザもやがて再婚したが 6、精神を病み、生涯の最後の10 年間はコルフ島の精神病院で過ごした。ハーンは人づてに母親が再婚したことは聞いたが、精神病院に入ったことも知ったかどうかは定かではない。
ハーンは父方の裕福な大叔母に育てられ、その援助により王子様のように素晴らしい大学生活を送りフランスに留学 7もしたが、他方、厳格で「ピューリタン的」な生活様式に嫌悪も感じ、反抗的で攻撃的な人格を形成していった。しかし、大叔母の破産によって、ハーンは学業を中断せざるを得ず、人生のどん底に転落した。アイルランドを出国し実家の乳母だった女性を頼ってロンドンに渡り、約3年間滞在したが極貧の生活を送ったらしい8。結局、片道切符を手に若きハーンは「新世界」アメリカ行きの船に乗り込む。夢物語は終わり、王子様は素寒貧の移民となっていた。
(イ)アメリカ時代 第二時代であるアメリカ時代にも様々な経験をするが、事態は徐々に好転していった。 アメリカでの最初の数年はヨーロッパ時代末期のように絶望的だったが、ギリシャ人移民としてのDNA(粘り強さ、意思の強さ、不屈の精神等)が目覚めたらしい。一日中肉体労働 9をした後、書物との接触を失わないために夜はニューヨーク市立図書館に通った。経済的に余裕が出来た時、ハーンはシンシナティへ向かった。親戚はあてにならず、いくつかの事業に挑戦したが失敗した。しかし、思いがけずH・ワトキン 10の助けで、印刷所で論文などの校正作業をする職を得た。ハーンは隻眼11だったため仕事は相当な疲労を伴なったが、独り立ちした後も恩を忘れず、手紙でワトキンを「ダディ」と呼び、自分のユーモア溢れるイラストを贈っていた。(ハーンは絵にも才能があった。)ここからハーンの人生は上り坂が続き、シンシナティとニューオリンズで記者として活躍し、ニューオリンズでは、南部のラテン的要素に惹きつけられて約10年間滞在した。アメリカでは翻訳業も開始した。事件報道から文学に対象を移し、中編小説『チータ』と『ユーマ』を発表した。これらはハーンが後に持つことになる社会学的課題への関心の兆候を示し、当時のアメリカ文学を「詩的散文」で復興させるというハーンの着想の一端を見せている作品である。 さらに、アメリカからは仏領西インド諸島にヨーロッパと比べて比較的簡単に旅行出来た 12。同諸島のマルティニークには約2年間滞在した。ハーンの愛情と関心は常にマイノリティへ向けられていたので、クレオール人をテーマにし、『仏領西インドの二年間』を執筆した13。ハーンは四十歳にしてなぜ成功していた職業を捨ててアメリカを離れたのか。人生を一から始め直すようなリスクの多い決断をし、東洋へ流浪の旅を続けた理由としては、第一に偶然の要素が考えられる。ハーンの東洋との最初の出会いは、ニューオリンズの万国博覧会で中国館や日本館を訪問した時だった。その約5年後、米大手月刊誌ハーパーズマンスリーマガジン 14により日本へ派遣され、「日出ずる国」で臨時の仕事をした。偶然以外の要素としては、アメリカではプラス面もあったが、ハーンの理念に反することが多々あったためだと考える。 例えばハーンは、アメリカの工業化・機械化された生活様式に対する恐怖を示している。また、ハーンの美的感覚は西洋古典美術により育まれており、アメリカで有力になりつつあった現代西洋美術を嫌悪していた。さらに、ハーンは混血女性と関係 15を持った程、当時アメリカでまだ根強かった人種差別を嫌悪していた。加えて、ハーンの民族的アイデンティティーの問題もある。ハーンは「世界市民」となってはいたが、自らの帰属先に疑問を抱いていた。渡米する前からアイルランド的側面は拒絶していた反面16、ギリシャ名は保持するなど、自分自身のギリシャ的側面にこだわりを持っていたらしい。しかしこのギリシャ的側面からも完全な満足を得られなかったようである17。ハーンは弟のダニエル・ジェームズの存在も知るが、アメリカ式の考え方や生活様式を持つ弟は、ハーンの内的不満解消の助けとなることは出来なかった 18。ハーンは自分自身の心の空洞を埋める努力を常に続けていく中で、最終的に日本へと歩んでいったのだと思う。
(ウ)日本時代
第三の日本時代は、彼の国際的な評価や評判が定着した時代でもある。 アメリカ時代からの関心事や、記者活動は継続していた。また、彼の関心は伝統的で庶民的な題材の豊富な日本の怪談や怪奇物語へ移り、彼の「詩的散文」の着想は和文へと向かっていった。しかし、職業活動や生活様式は、アメリカ時代に比べて決定的に変化した。 ハーンの日本での職業人生は、四つの町に織り重なる。 第一のゆかりの町は松江。ここでハーンは、日本の自然美、自分自身とよく合う日本人気質、伝統や習慣に最初の衝撃を受けた。英語の教育を始め、小泉セツと結婚 19。日本名小泉八雲を名乗り、後に日本に帰化した。第二の町は熊本で、教育と著述に没頭し、約3年間滞在した。 次の町は神戸で、約2年間滞在し、地元英語紙の神戸クロニクル等での記者業と著述業に没頭した。 最後にB・チェンバレン東京帝国大学教授 20に推薦されて上京し、生涯最後の約7年間を大学教授として務めた21。同時に記者としての豊富な経験を活かし22、現在も世界中で愛されている日本に関する題材豊かな名作をアメリカで出版し続けた。1904年に死を迎えた際は教え子等にまで惜しまれた。松江の小泉八雲記念館の記念碑に感動的な銘文を残したり、費用を持ち寄りハーンの講義記録集を出版した学生もいた。ハーンの日本での滞在先や訪問地には、記念館や記念碑が今でも数多くある。
2.教育者としてのハーン
西洋では教育者としてのハーンは彼の著述ほど知られていないとの見方もあるが、私たちギリシャ人、特に教育者達にとっては重要な意味を持つと思う。例えば、ハーンは日本の教育システム、学生気質、ヨーロッパと日本の教授法の差異等について色々と書き残しているが、これらの集約や研究は歴史的研究としても大きな意義があると考える。 教育者としてのハーンは、友人による仲介、一家の主であることに伴う制約、完璧主義、日本での大学教授資格を有しない等多くの不安定要素があったにもかかわらず、大きな成功を収めた。 成功の理由としては、ハーンの教育基盤、学生に対する純朴で素直な接し方、そして独特な教授法が挙げられる。ハーンは、西洋では一般的教育法であった普遍化された理論的専門研究を断固として退け、日本と西洋の具体例を挙げながら教えた。中国を起源とする日本の伝統文化のように、英文学を理解するにはギリシャ・ローマ文化が欠かせないと説き、古代ギリシャ文化へ視点を向けて比較研究を進めた。こうした中で、ハーンは古代ギリシャ詩の中に日本と同じような習慣 23、例えば、音色を楽しむために「歌う虫」をかごなどで飼うことを発見し、虫の種類の類似も指摘している。また、ギリシャ人と日本人が取り扱う主題の近似性も指摘している。例えば、子供を亡くした親の詩では、日本の父親は、幼い我が子が疲れてしまうことを案じ、黄泉の国の使者に子供を運んでくれるよう願い、ギリシャの父親は、同じように子供に手を貸してくれるよう死者の国の渡し守に願っている。ハーンは、このような研究を続け学生の心を捕えた。
3. ハーンのアイデンティティー 比較研究をする中で、ハーンは自分自身の中に積み上げられていたアイルランドやアメリカでの経験の上に新たな「日本的」世界を構築していき、これは徐々に「ギリシャ・日本的」世界となりつつあった。模索しつつハーンは、 恐らく― 初めは無意識の内に― 自分の苛まれたアイデンティティーを統一していったのだろう。日本文化により深く触れていくに従い、ハーンは日本で自分のアイデンティティーのギリシャ的側面をより一層意識していったのではないだろうか。ハーンは少年時代に書物を通してギリシャ文化の外見的な美しさに魅了されていたが、その発祥地ギリシャで体験できないまま自分自身との内なる関連性を意識するには至っていなかった。「日本」は、ギリシャ文化という一つの文化を、ハーンに対し深く理解させたのだと思う。
4.今日のギリシャにおけるハーンのイメージについて 日本にはハーンの孫や曾孫 24がおり、その内の幾人かはギリシャへの訪問経験がある。日本とアイルランドにおけるハーンの系譜は体系的に研究されており、アイルランドはハーンとの関係を国際的に強調する努力を続けている。それに対し、ギリシャでは、既存の資料を包括的に発表する計画的な共同作業等がなされておらず、主にハーンの日本とアイルランド的側面のみが知られており、ハーンの系譜は完全には研究されていない25。しかし、ギリシャにはハーンに関する多くの記念碑がある。例えば、キシラ島にはローザの家(写真1, 2)や第二の家族と共に眠る墓(写真3)がある。レフカダ島には、趣ある「小泉八雲通り」(写真5, 9)にハーンの生家(写真5)があり、すぐ近くには洗礼を受け名前を授かったアギア・パラスケヴィ教会(写真6)もある。同島の海辺の広場にはハーンの胸像26(写真8)があり、ハラモグリオス図書館27(写真10)にはハーン専課(写真11)もある。ハーンの研究にかかわり、日本とギリシャに駐在経験がある外交官としては、K・ヴァシス元大使や、二ノ宮元参事官、大久保元大使がいる 28。
5. ハーンのギリシャ名。-なぜ(英語で)aで綴ったか- ギリシャ人は、ハーンの名前の由来 29を知っているので、どう書かれていようとも「レ」フカディオ(ス)と発音する。日本では、英語から日本語に書き換えられた名前を発音し、「ラ」フカディオで定着している。因みに、英語の母音の音声は単一ではない。ハーンは、普通イーと発音される英語のeか、日本語やギリシャ語のアとエの中間位の音で発音されるaかの選択に迫られた時、音としてより親近性のあるaを自然に選んだのだと思う。この単純な自説に対しては、日本人学者から色々な反応があった。例えばギリシャの役所と英語で書簡を交わす時、「Lafcadio」と書くのに「Lefcadio」と返信されたことの疑問が解けたとか、逆に、ハーンはギリシャ語を知らなかったのだからこのような判断が出来るはずがなかった等の反論もあった。しかし自分としては、ハーンは学問的に考えることなく名前を英語に書き換えたのではと推測する。ハーンは視覚に障害があったので、より鋭く研ぎ澄まされた彼の聴覚が唯一求めていたのは、愛しい音(遠い過去、レフカダ島でやんちゃな彼の名前を呼ぶ母親の高らかな声)の再現であり、要は心の問題であったのだと思う。 自分としては、英語ではLafcadioとしながらも、同時にLefkadio(s)、レフカディオ(ス)と記載されるべきだと考えるし、日本語のエは、ギリシャ語のε(エプシロン)と同じ発音なのだから、日本人にもこの書き方を是非使ってほしい。
6.「母」ローザ ハーンは早くから母親と疎遠になっていたはずで書簡などでもめったに母親に触れていない等との反論については、視点を変えれば、これらは逆の事実を示しているとも解釈できる。ハーンは個人的な事柄について話す時は非常に慎重だった反面、驚くほど胸襟を開くこともあった。例えば、弟にローザについて子供の頃の細かいことまで語る等、曖昧といえない記憶を持っていたことが覗える。さらに、ハーンの作中の女性が、ローザとの関連においてしか理解できないことも指摘されている。 ハーンは、日本のごく普通の女性、特に母としての女性に対し敬虔に近い気持ちを抱いていた。日本人女性像に、時とともに昇華されていく薄明かりにたゆたうローザの像を重ねていたように思う。その極め付けは、ハーン自らが『夢想』 30と題した、短い文学傑作にある。この中でハーンは、惑星・地球の壊滅を幻想し、廃墟の中から浮上し蘇生させる大古からの全宇宙の母神像と混沌を対立させる。この「像」は、ローザに対する賛歌であろう。なぜならよく読むと、これは芸術家として成熟した一人の男性による文学的描写ではなく、逆に子供の目で見た幻想表現であることが分かる。ローザを連想させるこの文章の骨子は: 1)母親の微笑みのひかり、2)接吻の激しさ、3)甘い子守歌、4)優しい信仰、5)胸から溢れるネクタル、である。 幻想の無邪気さと象徴化は明白である。同時にこの幻影は、ハーンが自分の人生において抱き続けることができた唯一の紛れもない母親像である。ローザは、今や幼いハーンのベッドにかがみこんで指で十字を切らせてはいないけれども。遥かなる高所より、つまりラフカディオ・ハーンともはや遠くない未来において再会することになる超自然的な世界に佇み、我が子を見つめているかのようである 31。
本翻案や本インタビューの見解や所見は、日本国政府や在ギリシャ日本国大使館のものと必ずしも一致するものではありません。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
         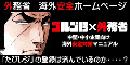             
 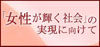  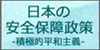 
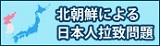        
|
法的事項|アクセシビリティーについて|プライバシーポリシー |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Copyright (c) : 2014 Embassy of Japan in Greece
46 Ethnikis Antistasseos Str., 152-31 Halandri, Athens [ Phone : +30-210-6709900 (Central) | Fax : +30-210-6709980 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||