ハーンの曾孫・小泉凡と小泉夫妻によるインタビュー |
||||||||||
|
来年、小泉八雲没後110周年を迎えるにあたり、八雲の生誕地、レフカダ島で記念行事を企画されている小泉凡・祥子夫妻が今夏、同島を訪れた際、インタビューを行いました。小泉凡氏は、民俗学者、島根県立大学短期大学部総合文化学科教授であり、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲/1850-1904)の曾孫として、小泉八雲記念館顧問を務め、祥子夫人とともに小泉八雲を通じた松江市の文化国際交流に積極的に取り組んでおられます。
  質問: あなたにとって小泉八雲はどのような存在ですか。 凡氏: 年齢によって感じ方が変わっています。 8・9歳の頃、児童向け伝記シリーズを出すという出版社の方が取材に来られ、庭で八雲の遺品の望遠鏡をもってモデルになった時に、はじめて先祖に著名な作家がいるのだと気付きました。その後、旅好きが高じて民俗学を専攻し修士課程に進んだ時、「アメリカの民俗学者、ラフカディオ・ハーン」というアメリカ民俗学会誌の論文を読んで、目から鱗が落ちました。民俗学の草分けの仕事をしたフォークロリスとしての敬意を持ちました。 いまでは、曾祖父は、彫刻家イサム・ノグチの父である野口米次郎が語ったように、「予言者?」なのかと思っています。「自然災害と日本人の気質」「自然との共生の必要性」「シンプルライフを維持することの大切さ」「五感研ぎ澄ますことの意義」「怪談の中の真理」「教育の課題」など現在社会のニーズにこたえるメッセージを100年余り前に遺しているからです。 祥子氏: ひと言で申しますと、守り伝えていくべき人でしょうか。ハーンの言葉には学ぶべき多くのことがあります。 この宇宙の中で生きている「自分」というものを、多様な視点から見つめ直すための何かを問いかけてくれる人だと思います。 質問: あなたにとって小泉八雲のひ孫夫妻でいることは、どのような意義を持っていますか。 凡氏: 近年、「文化資源」という概念が注目されています。未評価の文化を発見・発掘、プロデュースし、ツーリズム・地域振興・文化創造などに生かそうという実践です。つまり文化と社会の垣根を低くしようという考え方です。この着想に基づいて、ハーンの事績や精神性を現代社会に生かす実践活動を行うこと、これが現在、子孫としての意義を感じている点です。たとえば、ハーンの「怪談」をツーリズムに生かした「松江ゴーストツアー」は、のべ実施回数がまもなく200回、参加者は3000人に達しています。ハーンの五感力を子どもたちに継承する教育実践「子ども塾―スーパーへるんさん講座―」も(毎年夏休みに実施)、今年で10回目になりました。ハーンの偏見の少ない開かれた精神性を現代アートで表現する造形美術展 ”The Open Mind of Lafcadio Hearn”は、2009年10月にアテネのアメリカン・カレッジで開催されたのを皮切りに、その後松江、ニューヨーク、ニューオーリンズなどハーンゆかりの地で、主に家内が中心となって展開してきました。 祥子氏: 小泉家に対しての尊敬と継承の念です。一人息子には、「小泉八雲の子孫です」と胸を張って言える人になってもらえればと思っています。 質問: 来年7月に行われる小泉八雲没後110周年記念行事の概要と、読者の方々へのメッセージをお願いします。 凡氏: 【ギリシャ小泉八雲没後110年記念事業の概要】 この企画、オープン・マインド・オブ・ラフカディオ・ハーン 「西洋から東洋へ」は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が持つ「オープン・マインド(開かれた精神)」を、彼の著書や手紙・講義録などを通して、多角的な視野で分析・解釈を試みるシンポジウムで、ハーンの生誕地レフカダで開催するものです。このシンポジウムの開催にあわせて、レフカダ文化センター内に「ラフカディオ・ハーン記念室(ラフカディオ・ハーン・オープン・マインド・ラーニング・センター(仮称)がオープンする予定です。そこには日本のハーンゆかりの各地から展示品のレプリカが寄贈されます。 その他、関連イベントとして、ハーンが3年間居住した熊本県の山都町(旧清和村)に150年前から伝わる人形浄瑠璃、清和文楽によるハーンの「雪女」公演とハーンの第二の故郷松江で毎年解散されている、松江出身の俳優佐野史郎とギターリスト山本恭司によるハーン作品の朗読ライブをレフカダで実施します。 【伝えたいこと】 まずは参加者の皆様に、ハーンにとって始原の地の大気の感触に触れ、レフカダはじめギリシャの自然と文化の魅力を感じていただくこと。そして、シンポジウムを通して「偏見のない美意識」「人間中心主義への警告」「偏見のない人種観」「開かれた耳と音楽観」など、現代社会に必要なハーンの開かれた精神性を感じ、今後どのように社会に生かすことができるのかを、それぞれ考えていただくことです。 文楽や朗読ライブでは、日本の伝統芸能の魅力を存分に味わっていただくとともに、生涯「語り」を愛しやまなかったハーンが耳を傾けて聞いたイマジネーションの世界を体験していただきたいと思います。 祥子氏: 5年ほど前のアテネで開催されたハーンをテーマにした美術展以来、小泉八雲は世界の中でさらに注目される存在となりました。 そんな中での没後110年の国際シンポジウムは、常に旅人であったハーンを通して、世界中のゆかりの地からハーンのオープンマインドを解釈するという試みであるとともに、「なぜ今ハーンなのか?」ということの意味を、シンポジウムを通して自分なりに考えていただく機会になればと思います。 文学者としてのハーンの枠を解き放ち、アートへとツーリズムへと教育へと彼の存在意義は変わりつつあります。 そして、ハーンの原風景である生誕地レフカダでシンポジウムが開催され、それが世界へと発信されていくことに大きな意義があり、さらに、将来のレフカダでの活動へと つながっていく一助になればと思います。
|
||||||||||
         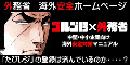             
 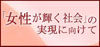  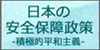 
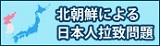        
|
法的事項|アクセシビリティーについて|プライバシーポリシー |
|||||||||
Copyright (c) : 2014 Embassy of Japan in Greece
46 Ethnikis Antistasseos Str., 152-31 Halandri, Athens [ Phone : +30-210-6709900 (Central) | Fax : +30-210-6709980 |
||||||||||