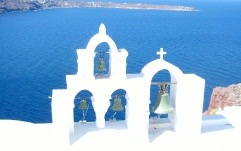2014年3月18日と19日、アテネ・コンサート・ホール(メガロン)で、「狂言 欧州・中東三カ国巡回公演」のアテネ公演が行われました。公演団長を務めた狂言師の山本則俊氏にインタビューしました。
 - 狂言とは一言でいうと何ですか。
- 狂言とは一言でいうと何ですか。
一言で言うと、狂言は仕草と台詞からなる喜劇です。狂言には約200のレパートリーがあり、生まれてから死ぬまでの人間の一生の中で、罪になる一歩手前の生活のエピソード(人間の愚かしい姿)を切り取り演じることで、観客の同意と笑いを引き出します。能は謡と舞からなるシリアスなドラマで、観客が声を立てて笑う要素は含まれてはいませんが、能と狂言は表裏一体で、水と油の関係ではなく、お湯と氷の関係です。能と狂言は一見すると、明と暗、悲劇と喜劇と正反対に見えますが、共に人間の生き様を多面的に扱い捉えている点が共通しています。
- 狂言の舞台の特徴は何ですか。
狂言は能とともに約650年前に劇として完成しました。26~27代前の先祖が生きていた時代から途絶えることなく現代まで続いています。狂言の舞台上には何の設定もありません。狂言では、演技者の仕草と台詞のみで、舞台上に様々な空間を描き出します。舞台背景の松は「陽向の松」といい、大自然の象徴であるとともに、神様も舞台を見ているという意味もあります。狂言師が出入りする揚幕は、宇宙(木、火、土、金属、水)を表しています。
- 狂言師という仕事について教えて下さい。。
欧州、北米、アジア等、これまで海外公演の経験は多いのですが、自分にとってアテネでの公演は44年ぶりです。狂言専業としては江戸時代末期から4代続く狂言師の家系に生まれました。山本家の家訓は、「乱れて盛んなるより、固く守って滅びよ」です。江戸幕府の式楽の系統を守り、今後も国内・海外公演に力を入れていきたいと考えています。